『機嫌のいいチームをつくる』を読み、選手が主体的に成長し、チームを勝利へと導くための監督の哲学と具体的な実践方法について深く学ぶことができました。
特に、「主体性」の重要性とその自己決定がもたらすプラス効果、そして心理的安全性の高いチームを構築することの意義は、スポーツチームのみならず、あらゆる組織運営に通じる本質的な洞察を与えてくれます。
本書の概要
本書は、プロ野球の監督が、選手が主体的に「勝手に」成長していくための環境を整え、すべての関係者がチームの勝利に貢献できる「心理的安全性の高い」「機嫌のいいチーム」をいかに構築するかについて、その哲学と実践方法を説いています。
リーダー(監督)が「選手のため、チームのため」という確固たる軸を持ち、すべての責任を引き受けながら、情報開示と徹底したコミュニケーションを通じて、主体的な思考と行動を促す環境を整えることの重要性を強調しています。
主要なテーマと私の学び
1. 「主体性」がチームと個人の成長を加速させる
本書で最も印象的だったのは、「主体性」と「自主性」の明確な区別です。
- 主体性: 自分自身の意思や判断に基づいて行動を決定する様子
- 自主性: 当然になすべきことを、他人から指図されたり、他人の力を借りたりせずに、自分から進んでやろうとする様子
この両者の大きな違いは、主体性には「自分の意思や判断」が含まれる点にあり、これがモチベーションに大きく影響します。
自分で決定した行動は、人から指示された場合よりも高いモチベーション、集中力、そして持続力をもたらすと述べられています。調子が悪くなった際にも、すべてを自分で決めていれば、何が悪いのかを振り返りによって認識しやすくなるため、主体的に自己決定をしていくことは、スポーツ選手にとってあらゆる意味で大きくプラスになると強調されています。
選手が主体性を持てば、自分の特徴やできることを正確に把握し、自分ができることに集中できるため、個性を発揮しやすくなります。
2. 「機嫌のいいチーム」が「強いチーム」である理由
「機嫌のいいチーム」とは、単に雰囲気が良いだけでなく、選手が主体的に成長し、すべての関係者がチームの勝利に貢献できる心理的安全性の高いチームであると定義されています。このようなチームこそが「強い」チームであり、リーダーにはそのための力量が求められます。
心理的安全性を確立するためには、以下が重要であると学びました。
- 情報開示の徹底: 監督があらゆる情報をオープンにすることで、チームの透明性を高め、選手に考える材料と準備の時間を与えます。
- 多様な意見の尊重: 知識や経験のレベルに関わらず、臆さずに意見を言える環境を構築することが重要です。野球経験のない栄養士の意見からも新たな気づきが生まれる可能性が示されており、「チームを一度壊さない限り、新しいものは生まれない」という監督の覚悟が示されています。
- 失敗を恐れない文化: 失敗した選手を叱るのではなく、何ができて何ができなかったか、なぜできなかったかを選手自身に語らせ、次にどうするかを明確にするプロセスを重視します。監督自身が失敗の原因をオープンにし、コーチやスタッフに意見を求める姿勢が、心理的安全性を担保するとされています。
3. 監督・リーダーの役割とコミュニケーションの力
監督の役割は、選手に主体性を持たせ、自ら考え、決断し、行動できるようになってもらうための環境を整えることであると明確に示されています。そのために、監督は以下のことを行います。
- 基本方針の確立と全責任の引き受け: 「選手に主体性を持たせ、自ら考え、自ら決断し、自ら行動できるようになってもらいたい。そのためにできることはすべてやる」という覚悟をもって基本方針を決定し、コーチ陣を信頼し、責任を引き受けます。
- コミュニケーションをチームの土台とする: チームのメンバー全員が互いを熟知し、リスペクトし、影響を与え合う組織こそが最終的に勝利するとされています。特に「質問」の重要性が強調されており、相手を否定せず、答えを押しつけず、質問を重ねることで選手の主体性を育み、信頼関係を築きます。コーチングは「凧揚げ」に例えられ、適切な質問で選手の気づきを促すことが重要です。
- 勝利と育成の両輪推進: 中長期的なチーム戦略には、勝利を目指す部分と育成の部分が両方不可欠であり、勝利は選手が自らの思考の正しさを確信し、考える習慣をドライブさせるために必要であるとされています。
- コーチの育成: 監督はコーチ育成を重視し、「ビジネスで言えば、トップが中間管理職をどう育てるかという視点だ」と述べています。コーチが選手の主体性を育むサポートができれば、選手は自ら成長していくと信じられています。
4. 相互作用によるチーム力の向上
選手個々が主体的に自己決定を重ねて成長した結果、新たな視点を獲得し、それを他の選手に向けることで、自分だけでなく他の選手にも気づきを与えられるようになると本書は示唆しています。
この相互作用によって選手はお互いに成長し、それが最終的にチーム全体の力を高めることにつながります。「キャプテン不在のリーダーシップ」という概念も提示されており、選手個々が主体性を持てば「誰もがキャプテンになれる」という考え方が、この相互成長を促進します。
本書から得られた示唆と実践したいこと
本書は、単なるスポーツチームの運営論にとどまらず、個人が自律的に成長し、組織全体が協調しながら成果を最大化するためのリーダーシップ論として非常に示唆に富んでいます。
私自身の気づき
プロジェクトを進めるなかでも、この考え方は強く共感できます。例えば、若手メンバーが「作業的になってしまう」ことが課題になりがちですが、安心して意見を出せる場を整えることで、思わぬ改善提案が生まれることもあるでしょう。
「チームをどうまとめるか」ではなく、「メンバーがどうすれば自分から動きたくなるか」を考える。これこそがリーダーシップの核心なのだと思います。
今後の活動に活かしたいこと
- 「主体性」を尊重する環境作り: 指示するだけでなく、相手に考えさせ、自己決定を促すような質問を心がけ、内発的なモチベーションを引き出すコミュニケーションを意識する。
- 心理的安全性の確保: 失敗を許容し、意見を言いやすいオープンな雰囲気を作り出す。自分自身の失敗も開示することで、相手の心理的ハードルを下げる。
- 「問い」の質の向上: コーチングにおける「質問力」の重要性を意識し、相手の思考を深掘りできるような問いかけのスキルを磨く。
- 長期的な視点での育成: 目先の成果だけでなく、個人の成長とその先のチームへの貢献を見据えたアプローチを取る。
おわりに
この本は、リーダーシップとは、単に指示を出すことではなく、個々が自らの意思で輝けるよう、思考と行動の自由を保障し、その成長を最大化する環境を構築することであると強く訴えかけています。
監督の思考と行動が、最終的に「伝えられた内容を、自分の頭で考え、何が原因か模索し、どうすれば克服でき、どうやって行動するかを自分で決めてほしい」という一点に結びついているという言葉は、まさに本書の核をなすものだと感じました。
この哲学こそが、「機嫌のいいチーム」が勝利と成長を両立させる秘密なのだと深く納得しました。
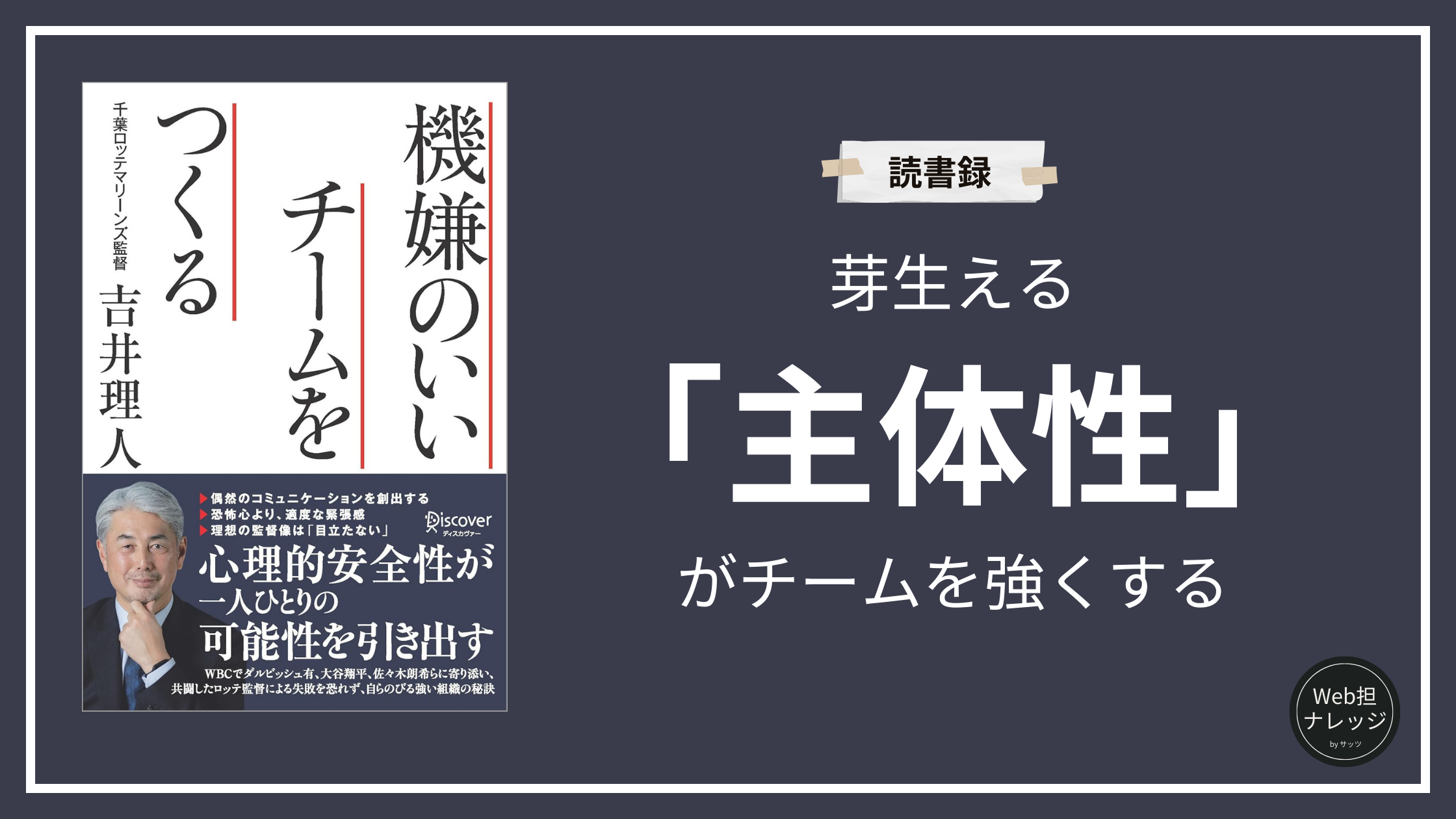

コメント